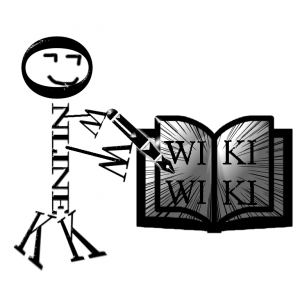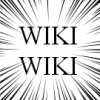| 青梅市カルト児童集団監禁事件捜査資料:被害児童のものと思われる手記(4)
お母さんごめんなさい。本当にごめんなさい。ここから出してください。ここはせまくて暗いです。カッターで切られたあとが痛くて涙が出てきます。もう生ごみを食べるのはいやです。トイレも無いので臭くて気持ち悪いです。ここから出してください。僕は偽者ではありません。お母さんごめんなさい。暗くて人が少ないから行くなっていつも言われていたのに、あの時近道から帰ろうとしてごめんなさい。許してください。
月刊テンポ・ルバート2014年5月号掲載「奇妙な儀式と未解決事件……9年前に消えた謎のカルトを追え!」
先日の「瀬戸内海の人魚伝説」の調査も終わり、一息ついた「となりのオカルト調査隊」。そんな我々の元に、新しい調査依頼が舞い込んだ。依頼人は、神奈川県某所在住の白坂憲二氏(74歳男性・仮名)である。
「私は、息子夫婦が入会していたある『団体』のことを調べてもらいたいんです」
白坂氏は、調査隊を自宅に招き、こう語った。彼の深い皺には、往年の苦労が刻まれているようだ。
「私たちは、それは仲のいい家族でしたよ。私と女房、それに一人息子の三人で、笑顔の絶えない家庭だった。やがて息子が結婚し、実家を出ていくと、少し寂しくなりましたけどね、時々孫の綾香(編集部注:仮名)を連れて遊びに来るんです。それがもう、お爺ちゃんとお婆ちゃんには嬉しくてたまらないんですよ。綾香はよく懐いてくれました。おもちゃも沢山買ってあげましたよ。お嫁さんもいい人でねえ、うちの女房と会ったその日から友達みたいに仲良くなって。こんな幸せがずっと続くと思っていた。……しかし、そうはならなかったんです」
調査隊も、重い空気を感じ取った。白坂氏は、固く拳を握りしめて続ける。
「忘れもしない、11年前のことです。一家で夏祭りに行った日だった。綾香はもう9歳になっていました。花火を見たり、出店で遊んだりして、夜も遅いしそろそろ帰ろうか、となった時、綾香がトイレに行きたいと言い出したんです。ちょうど私の女房もトイレがしたかったから、息子夫婦が車を取りに駐車場に行く間に、私と女房で綾香をトイレに連れて行くことになりました。私は女子トイレの前のベンチで待っていましたよ。するとね、しばらくして、女房が真っ青な顔で出てきて、『綾香がいない!』と言うんです。
どうやらトイレは相当混雑していたみたいで、女房が用を済ませて出てくると、もう綾香の姿は見えなかったらしい。……それから私たちは必死で綾香を捜しました。もちろん、警察も必死で捜してくれました。それなのに、一日経っても、二日経っても、綾香は見つかりませんでした。誘拐されたんです。女房は、自分のせいだと言って、息子夫婦に泣いて謝りました。しかし、トイレの外にいた私が注意していたら、こんなことにはならなかったかもしれない。息子夫婦は私たちを責めるようなことはしませんでしたが、とにかく、あの日を境に、家族はバラバラになってしまったんです」
日本では、毎年千人を超える児童が行方不明になっている。その多くはわずか数日で発見されるが、中には何十年経っても消息がつかめない例もあるのだ。綾香ちゃんも、失踪から11年が経った今なお、その行方はおろか生死すら分かっていない。
「それからは、捜査の進展も全くなく、息子夫婦とはどんどん疎遠になっていきました。……本題はここからです」
我々は、いっそう身を引き締めて話に聞き入った。
「あれから一年ほど経った後、息子夫婦から手紙が届いたんです。まだメッセージのアプリなんかもありませんでしたからね。手紙の内容は、息子夫婦が『関東地方誘拐被害児童の家族の会』という団体に入会したという話でした。それで、彼らの会には被害児童の持ち物や服などを会に納めて無事に帰ってくることをお祈りする取り組みがあるんだそうで、それが『セキホウ』……と読むのかは知りませんが、『痕跡』の『跡』に『奉納』の『奉』で、『跡奉』。そういう名前だったんでしょう。私らに、『跡奉のために、綾香に関係する物がもし残っていたら渡してほしい』と言うんです。正直、少し……強引さというか。そういうものを感じなかったわけではありませんが、負い目もあったし、特に拒む理由もないと思って、綾香のために置いてあったおもちゃや服を指定された宛先に送りました。『家族の会』の施設の住所だということでした。
それからまた一年くらいした後、警察から電話が来ました。綾香の件で何か進展があったのかと思いましたが、そうではありませんでした。……息子夫婦の死体が、発見されたんです。それも、遠く離れた栃木県のとある山に埋められて窒息死した、明らかな他殺体だったそうです。私も女房も、愕然となりました」
白坂氏は大きな呼吸を置いて、再び話し始めた。
「事件の取り調べの中で、息子夫婦の交友関係について尋ねられた時、私はその『家族の会』のことを話したんです。すると、警察の方は驚いた様子で、慌ただしくどこかに連絡し始めました。なんでも、ちょうどその当時、この会に関わる捜査が別件でなされていたんだそうです。詳しいことまでは、教えてもらえませんでしたけどね。……しかし、結局、息子夫婦の事件も迷宮入りになってしまいました。不思議なことに、息子夫婦には抵抗した痕跡が見つからず、犯人の痕跡も一切残されていなかったそうです。
それからは、心の傷も癒えぬまま、二人でひっそりと暮らしてきました。あの団体のことなんて忘れていましたよ。ただ女房は、年のせいもあってか、次第に病気がちになってしまってね、半年前にぽっくりと逝ってしまいました。……しかし、ほんの数日前のことです。女房の部屋で、遺品を整理しているとき、思いがけないものが出てきました」
そう言うと、白坂氏は机の上に一枚の封筒を置き、中身を出した。差出人は、白坂氏の息子になっている。そして消印は平成17年――息子夫婦の遺体が発見された年だった。
「息子は、殺される直前に、この手紙を家によこしていたんです。一体なぜ、女房はこれを隠していたのか……その理由は、すぐに分かりました。どうぞ、手紙の文面を読んでみてください」
荒い字でそこに書かれていた内容は、にわかには信じがたいものだった。
文章は、例の「家族の会」への称賛から始まる。「誘拐児たちを取り戻したいという切実な願いを持った親たちの強い結束」……さぞや立派な団体なのだろう。しかし、問題の記述によると、「家族の会」に属する親たちは、会が所有する施設内にいるという「ストーカー」と呼ばれているらしい人物に対し、殴る、蹴る、あるいは熱湯を浴びせる等の暴行を、日常的に行っていたというのだ。白坂氏の息子はこの「ストーカー」のことを異様なほど憎んでいるようで、「生きている価値のない人間の屑」などと貶め、この行為のことを誇らしげに書いている。また、詳細は書かれていないものの、そのような「誇らしい」行為のひとつとして挙げられている「きょうだいのお納め」も不気味だ。白坂氏の言うように「跡奉」が誘拐児童の痕跡を会に納めるものだとすると、この「きょうだいのお納め」は誘拐児童のきょうだいの身柄を会に納める行為であるとでも言うのだろうか? 手紙の最後には、「家族の会」の施設に五回目の強制捜査が入りいよいよ「危うくなってきた」こと、そして警察の手を逃れるために、近いうちに会が一旦「解散」するということが書かれていた。
「息子は責任感があって、真面目な子でした。……こんな異常なこと、見過ごすはずがありませんよ。きっとこの『家族の会』に変えられて、頭がおかしくなってしまったんです。あの団体は、危険なカルトだったんですよ!」
白坂氏の語気が荒くなる。
「すみません、少し取り乱してしまいました。とにかく私は、あの『家族の会』がどんなものだったのか、そして息子夫婦の身に何があったのかを、ただ知りたいんです。警察にはこの手紙のことを伝え、新しい有益な情報だったと感謝されましたが、捜査はやはり進展しないようだし、『家族の会』のことを聞いても当然詳しいことは教えてくれません。……しかし、下手に堂々と情報を募ることはできない。こんな田舎ですからね、『あの息子夫婦はキチガイのカルト信者だった』だとか、まず間違いなく近所で噂が立ってしまうでしょう。女房がこの手紙を隠していたのも、きっとそのためだったんです。これ以上、不幸な、かわいそうな息子夫婦の顔に、泥を塗りたくなかったんです。
本当にわがままで、愚かなお願いだということは百も承知です。聞けば、あなた方の雑誌では、実際に未解決事件を扱い、行き詰っていた捜査を一段進展させたこともあるらしい。……あれから九年経って、ようやく尻尾を掴めたんだ。しかし、こんな老いぼれ一人には何もできやしません。……どうか、お力を貸していただけないでしょうか」
そう言って、白坂氏は頭を下げた。「となりのオカルト調査隊」はもとより、神隠しや祟りのような超常怪奇現象から街角に巣食う怪しい宗教の都市伝説まで、社会の裏をくまなく扱うエキスパート集団である。この案件を断る理由がどこにあろうか? かくして我々は、白坂氏の素性を全面的に隠匿しながらも、この謎多きカルトの正体に迫るべく調査を開始することにしたのだ!
実は、我々は既に当時「家族の会」に関わりがあったという人物を見つけ出し、取材のアポを取ることに成功している。この情報は、次号に掲載することになる。この団体や事件について何か知っていることがあるという者は、すぐさま月刊テンポ・ルバート編集部オカルト係に問い合わせてほしい。それでは読者諸君、次号の「となりのオカルト調査隊」でまた会おう。
月刊テンポ・ルバート2014年6月号掲載「カルトに洗脳された妻……夫が覗いた怪しい施設の闇とは」
先月号の調査依頼を受け、我々は「関東地方誘拐被害児童の家族の会」の調査を開始した。その過程で連絡を取ることができたのが、茨城県在住の北口和也氏(41歳男性・仮名)である。
「こんな狭いアパートで、すいませんね」
我々調査隊が北口氏に連絡をとったきっかけは、インターネット上に公開されていた彼のブログである。そのブログは、いたって普通の家庭の生活を記録したものであったが、愛娘の失踪、そして「関東地方誘拐被害児童の家族の会」への妻の入会を書いた13年前の記事を最後に、更新が止まっていた。しかし、調査隊がブログのプロフィールに記載されていたメールアドレスにだめ元で取材依頼を送ってみたところ、なんと連絡を取り合うことに成功。こうして取材を取り付けるに至ったわけだ。
「私が22歳のころだから、19年前ですか。妻とは、当時勤めていた会社で出会いました。職場結婚ってやつです。大事な商談をダメにしちゃった時にも、励ましてくれたりして、気づいたら好きになっていたんです。その勢いのまま、プロポーズでしたよ(笑)。でも、後から聞いた話なんですが、そのとき既に妻は私のことを狙っていたらしいんですね。まんまと策に乗せられてしまったというわけです(笑)」
北口氏は楽しそうに過去を振り返る。部屋の奥にある棚の上には、家族三人の笑顔の写真が飾られているが、そこに写る北口氏はずいぶんと若々しいままだ。
「結婚してからすぐ、娘もできましてね。私ももう父親かと、なんだか感慨深くなったのを覚えています。娘は元気な子でね、休日にはいつもどこかに遊びに行きたいと駄々をこねて、私たちを困らせましたよ(笑)。あの時は、本当に楽しかったなあ。今でもたまにブログは見ています。娘の笑顔が、よく映っているんです。……そろそろ話を進めましょうか。小学校に入学して、もうすぐ二年生というとき、娘は誘拐されてしまったんです」
どこか遠くを見つめるように、北口氏は語る。
「きっかけになったのは、入学して半年ほど経って、学校にも慣れてきた頃でした。それまでは私たちが娘の送り迎えをしていたんですが、娘がある日『友達と一緒に登下校したい』と言い出したんです。家も近かったし、通学路も人通りが多かったので、私たちはそれを認めてあげることにしました。それから毎日娘は楽しそうに、友達と一緒に登下校をしていたのですが……あの時の自分の判断を、13年経った今でも強く悔やんでいます。そのせいで、娘はあの日、誘拐されてしまったんです。
そう、あの日……私たちは知らなかったんですが、いつも一緒に登校する約束をしていた友達が風邪で休んでいたみたいで、娘は一人で学校へ向かっていたらしいんです。そしてその途中で、誘拐されてしまった。娘が来ていないという連絡を学校から受けて、血の気が引きましたよ。警察にも連絡して、大規模な捜査が始まりましたが、一向に娘は見つかりませんでした。私も妻も、焦りと後悔で、パニックに陥りました。……そんなとき、妻が知ったのが、あの『家族の会』だったんです」
専業主婦だった北口氏の妻は、当時一般的になって間もなかったネット掲示板の書き込みから「家族の会」の存在を知ったのだという。そこから彼女は、日に日にその団体にのめり込んでいくようになったのだ。
「妻は、東京郊外にあるらしい『家族の会』の建物にたびたび行って、会員の方と交流するようになりました。彼女によれば、『家族の会』は不安や苦悩を親身になって聞いてくれて、いろいろな相談にも乗ってくれたそうです。私も当初、妻の話を聞く限りでは、何の変哲もない、それどころか素晴らしい団体だと思っていました。だから、妻が正式に『家族の会』に入会することになったときももちろん反対しませんでした。……後になってみれば、私はこのとき、またも選択を間違えたんです。
おかしなことが起こり始めたのは、それからすぐでした。妻が、娘の部屋にあった物をどこかに持って行ってしまうんです。最初に服やおもちゃを持って行ったときは、少し怪しいとは思いましたが、娘の好きなものを『家族の会』で共有しているのかと思って、自分を納得させていました。しかし、妻は一向にそれらを家に持って帰ってこないばかりか、しまいには娘の使っていた靴やランドセルまで持って行ったんですよ。流石におかしい。そう思って直接妻に聞いてみると、彼女は娘の物を勝手に持ち出して、『家族の会』で誘拐児童が帰ってくることを祈る取り組みに使っていたということが分かりました。先月号の記事も読ませていただきましたが、やはりこの儀式が『跡奉』というやつなんでしょう。……後で話しますが、私は施設の『跡奉』のために作られたという部屋にまで行ったんです」
「跡奉」――前回の依頼人も話していた、「家族の会」での儀式だ。誘拐の被害にあった児童の残した物を納め、無事に帰ってくることを祈るものだという。北口氏が覗いたその内実は、いかなるものだったのだろうか。
「妻は続けて、娘の物はただ施設に置いているだけであって、お焚き上げのようなことをするわけでもなく、きちんと管理していると言ってきました。しかし、それでも私の不安は拭えませんでした。妻はあの時、本当に娘の持ち物をすべて家から消し去ろうとしているくらいの気持ちに見えました。何というか、とにかく、異様だったんです。……でも、妻の話を聞く限りでは、『家族の会』は何の裏もない良い団体のように思えます。だから、ある日曜日、不安な気持ちを払拭するために、私も妻と一緒に『家族の会』の施設に行ってみることにしたんです。
カーナビに従い、数時間ほど車を運転して着いたのが、彼らが『本館』と呼んでいる建物でした。東京と言っても、かなり田舎の方で、近くの道路も往来はまばらでしたね。木々に囲まれた『本館』は、地域の小さい公民館くらいのサイズの、シンプルな青い三角屋根の一階建てで、壁は綺麗な白色をしていました。中に入ってみると、かなり重厚感のある内装で驚いたのを覚えています。壁は落ち着きのあるクリーム色で塗られていて、小さいシャンデリアのようなものが天井に吊り下げられていました。そこで妻に紹介してもらったのが、『家族の会』の代表という立場にあるらしい、アミさんという同年代くらいの女性でした。彼女は生まれつき聴覚に障害を持っているようで、私とは筆談でコミュニケーションをとりました。アミさんによれば、この建物は『家族の会』の先々代、すなわち四代目の代表が、被害者家族たちの憩いの場となるようにと造り上げたものだそうです。
そこから案内されたのは、奥の扉の先にあった少し大きめの部屋でした。そこでアミさんが、持ち運んでいたホワイトボードに『これは跡奉のための部屋です』と書いて私に教えてくれたんです。聞いたことのない言葉で戸惑いましたが、字面からうっすらと、妻が話していたあの儀式のことなのだろうと察しがつきました。鍵を開けてもらって部屋に入ると、その中にはたくさんの小さな仮設トイレのような個室が並べられており、私は妻に連れられて、その中の娘に割り当てられているという個室のところへ行きました。渡された鍵でロッカーのように扉を開けると、その中には妻が持ち出した娘の物が全てぎゅうぎゅうに収まっていて、妻は、これで納得しただろう、というふうにこちらを見てきました。……しかし私は、ますますこの団体のことを疑わしく思うようになりました。『跡奉』のやり方は、その目的とは対照的に、うまく言えないんですが……二重に鍵を掛けているところとか、無機質で、奇妙なように思えるし、それ以上に、私がいた間中ずっと、その部屋でかすかに子供の泣き声が聞こえてきたからです。妻によれば、親たちはみんな誘拐被害児童のきょうだいも連れてきていて、その子供がぐずっているだけだというのですが、聞こえてくる泣き声は明らかに赤ん坊のものだけではありませんでした。姿は見えず、どこにいるのかは分かりませんでしたが、物心ももうついているくらいの子供の声で泣いているのが、あちこちで聞こえてきたんです」
「跡奉」のための部屋に、その被害児童の「きょうだい」……この状況は、前回出てきた「きょうだいのお納め」という儀式に何か関係しているのだろうか?
「明らかに異常だとか、そういったことは断言できません。自分のきょうだいが誘拐された子供が、精神的に不安定になって泣いているだけなのかもしれないし、同じくストレスを感じている親にも、泣いている子供の世話をするだけの余裕が無かったのかもしれない。だから私は、口を出せませんでした。でも、子供の泣き声をずっと聞いていると、言いようのない不安でくらくらしてきて、ここにはいられないと思いました。妻に『もう帰ろう』と言うと、妻は大人しく、『分かった』とだけ答えました。……それから、アミさんにあいさつをして、二人で車に乗り込んだときでした。妻がいきなり、思い出したように『ちょっと別館の方を見てくる』と言ったんです。『すぐ戻ってくるから車で待っていてもいい』と言われた私は、もうこの施設に近づきたくなかったので、言われた通りに車で待っていました。
しかし、一つだけ気になることがありました。『別館』の場所です。入って来た時、正面から見たこの施設には、『本館』しか建物がありませんでしたし、『本館』の裏手にある駐車場からも、『別館』と呼ぶべき建物は見当たりませんでした。不思議に思って、妻が歩いて行った方向をリアガラス越しに見た瞬間、ぞっとしましたよ。妻は『本館』のすぐ裏で、地面の方を向いて、険しい顔で何かを叫んでいたんです。目が合いそうになったので、慌てて前を向きなおしました。……その後、何事も無かったかのように助手席に乗ってきた妻は、本当に私の知る妻なのかと、ひどく恐ろしくなりました」
北口氏が感じただろう、愛する妻への恐怖は、相当なものだったらしい。北口氏の表情は、過去を回想している中であってさえ、恐ろしげに歪んでいた。
「そして……娘の死体が発見されたのは、その日の夜でした」
目線を落として、北口氏は続ける。
「消息を絶ってから二週間後のことでした。娘は、他殺体で発見されました。首を絞められて……川に沈められていたそうです。その後すぐ、犯人も逮捕されました。娘は通学路で、車に乗せられて連れ去られ、その後すぐ……。すいません。まだ、このときの話は、うまくできません。とにかく、娘はもういない。もういないということが、分かったんです。分かってしまったんです。それなのに、それなのに妻は……まだ、あの団体で、『娘は戻ってくる』と、言い続けたんです! 必死に説得しました。私もつらかった。妻もつらかったんでしょう。そのせいで、あんなことになってしまったのかもしれない。でも、妻は、妻は……娘の遺体を見ても、『これは偽者だ』と言って聞かなかった……」
調査隊は、北口氏の目に涙が浮かんでいることに気づいた。
「すいません、取り乱してしまって。……私には、もう分からないんですよ。私はどうにか、妻がおかしくなった原因を、あの『家族の会』に押し付けようとしているのかもしれない。本当は、あの団体は何も悪くなくて、ただ妻は、妻の心は娘の死に耐えられなかっただけなのかもしれない。……その後、妻は失踪しました。今に至るまで、妻の姿は見ていません。一応、警察に捜索願は出しましたが、事件性のないただの痴話げんかによる家出として扱われ、捜索は行われませんでした。あの時の家からは、それから三年ほどした後、引っ越しました。こうして、今に至ります。……これが、私の話せる限りの、全てです」
北口氏の妻は、なぜ狂ってしまったのか、その答えを知る者はいない。しかし、先月号でお伝えした白坂氏の悲劇、そしてこの北口氏の悲劇の両方に深く結びつく奇妙な団体が、何かしらの形で一枚噛んでいるのはまず間違いないだろう。我々はこの団体の調査を続ける。この団体や事件について何か知っていることがあるという者は、すぐさま月刊テンポ・ルバート編集部オカルト係に問い合わせてほしい。それでは読者諸君、次号の「となりのオカルト調査隊」でまた会おう。
付記
北口氏への取材が終わった後、彼の携帯電話に非通知の電話がかかってきた。それ自体は何の特筆性もないことだが、電話を切った北口氏は奇妙そうに取材班にこう話した――非通知設定の、聞き覚えのないしわがれた高齢男性の声で、「ハマナソウキチくんをご存じですか」と尋ねてくる電話がかかってきた、と。
北口氏が戸惑って黙っている間に、電話は切れてしまったという。普通に考えればただの間違い電話だが、我々がこの出来事をわざわざ記録したのには理由がある。前回の取材時、我々が白坂氏の自宅を後にした直後、白坂氏から「見知らぬ長身の老人の男が山の方からこちらを覗いてきた」という連絡があったのだ。白坂氏は近隣住民に息子夫婦の件が嗅ぎまわられることを危惧しているようだったが、この奇妙な出来事は、我々の取材を追跡する何者かの存在を示しているのだろうか? オカルト記者としては、つい勘ぐってしまうところだ。
月刊テンポ・ルバート2014年7月号掲載「陥れられた夫婦は決定的瞬間を捉えた! 終わらないカルトの恐怖」
先月号の発売後すぐ、我々のもとに一件のメールが届いた。送り主は群馬県在住の谷美咲氏(37歳女性・仮名)であり、彼女はあの「関東地方誘拐被害児童の家族の会」の施設に夫婦で足を踏み入れたことがあるという。谷氏は取材に快く協力してくれた。
「あれは、加奈(編集部注:仮名)がまだ7歳の時でした。加奈は大人しい子で、休日はいつも家で本を読んで過ごしていました。でも、私たち夫婦はアウトドアが好きで、出会ったのも富士山の山頂なんですよ(笑)。だからあの日は、確か三連休だったから、家族でキャンプに行こうって決めたんです。今思えば、そのせいで……。ううん、そんなこと今になって言ったって、しょうがない話ですよね」
これまで取材した二名と違って、谷氏の表情には悲しさの中にもどこか余裕があるように見える。谷一家は娘を失う悲劇を経験したが、夫婦の絆が引き裂かれることはなく、今は後に産まれた加奈ちゃんの弟・理央くん(編集部注:仮名)と共に、家族三人で満ち足りた暮らしを送っているそうだ。理央くんは我々調査隊に興味津々で、本棚にあったUMAの図鑑を見せてくれた。オカルトライターとしては、彼の将来は有望だと言わざるを得ない。
「私も夫も、加奈との思い出を、悲しいものにしたくないんです。加奈はおっとりしていたけど、時々思いがけないようなことをする子で、いつも家では笑いが絶えませんでした。だから理央にも、あんまり暗い話はしていません。むしろ面白いお姉ちゃんがいたことを覚えていてほしいな、って思うんです。それが、あの子の生きた証になるのかな、って」
谷氏は顔を上げて続ける。
「すみません、前置きが長くなりましたね。とにかく……10年前のあの日、加奈はキャンプ場でいなくなってしまったんです。今でこそ私たちも落ち着いていますが、当時はもちろんパニックになって、警察の捜査を何もしないで待っていることに耐えられませんでした。そんな時、夫がどこかの雑誌から、あの『家族の会』の存在を知ったんです。私たちは、とにかく悩みや不安を誰かに打ち明けたくて、『家族の会』に連絡しました。その後すぐ、近所のカフェで会ってくれた会員の人は、同じ立場で、本当に親身になって私たちの話を聞いてくれました。私たちの味方はこの人たちしかいない、とまで思った記憶があります。……だけどそれは、人の弱みに付け込んだ、悪質なカルトへの入り口だったんです。
その会員は、『お祈り』だとか『おまじない』だとかいう言葉を使って、加奈が無事に帰ってくるために私たちにできることを紹介してきました。今思えばとんだ眉唾ものではありますけど、傷ついた私たちにとっては何よりありがたいものでした。そして、そのようなことをするための場所として、郊外にある施設のことを教えてもらったんです。スピリチュアルな話は置いておくにしても、同じ悩みを抱えた『家族の会』のメンバーが集まって交流する場所は、私たちの唯一の居場所のように思えました。だからその次の週末、私たちは早速その施設に行ってみることにしたんです」
谷氏の表情はだんだんと険しくなっていく。彼女もまた、前回取材した北口氏のように、奇異な施設の内部の姿を語り始めた。
「エントランスを抜けて通されたのは、やはりあの子供の物を納める部屋でした。『跡奉』って言うんでしたよね? 名前はそちらの記事を見て初めて知りましたけど。その中で、会員の人たちは、例の仮設トイレくらいの大きさの個室のいくつかを開けて中を見せてきました。カフェで事前に聞いた限りでは、私たちは『跡奉』のおまじないを少しスピリチュアルではあっても特におかしなものとまでは思っていなかったんですが、そのロッカー大の大きさの個室に子供のおもちゃや服とか、とにかく子供の物全部なんじゃないかっていうくらい沢山の物が敷き詰められているのを見ると、違和感を覚えました。子供のために祈るというなら、何もそんな小さなスペースに分けて施錠までしなくたって、広い場所を使ってみんなで一緒にやればいいじゃないですか。それに、持ってくる量も異常です。でも、ある個室の一つが開いた瞬間、その違和感は吹き飛びました。この施設はおかしい、という確信に、完全に変わったんです。個室の中に、猿轡を噛まされて座っている子供がいたんです!
夫が会員の人に問いただすと、あの人たちは悪びれる様子もなく、これは『きょうだいのお納め』といって、誘拐児童のきょうだいを誘拐された子供のものと一緒に納めているのだと言いました。……先月号に掲載されていた北口さんの話では子供の泣き声が聞こえたとありましたが、私たちが行ったのはおそらくその後で、泣き声が猿轡で対策されていたんだと思います。『跡奉』の部屋がああいう風になっている理由は、子供を閉じ込めるのに都合がよかったからなのかもしれません。その子供は無気力な表情でこっちを見ていて、そして……あの個室の床には、おもちゃや服の上で、排泄物が……そのまま、垂れ流しになっていたんです。とにかく、血の気の引いた私たちは、すぐにそこから離れることにしました。
すると、『家族の会』の人たちはそれを察知したようで、部屋の出口を塞ぐように立ちふさがって、私の腕をつかんだんです。あの人たちは私に何かを言おうとしていたみたいだったのですが……あの時感じた恐怖は、今でもありありと覚えています。私は悲鳴も出せず、足が震えて立ちすくんでしまいました。力の強かった夫は、大声を上げながら必死であの人たちを振り払い、私を担いで『本館』から逃げ出しました。後ろからは、私たちに何かを訴えかけるような感じの言葉が聞こえてきて……。気が動転していたからよく覚えていませんが、確か、『あのストーカーを見れば納得するはずです』『こうでもしないと本物が帰ってこないんだ』というような内容だったと思います。私たちはすぐに車に乗って、全速力であの施設を後にしました。震えながらバックミラーを覗くと、『本館』のすぐ裏……北口さんの奥さんが『別館』と呼んでいた場所で、あの人たちがこっちを見ながら、縄のようなものを使って誰かを引きずり出していました。遠かったし、こちらに背を向けていたのでよく見えなかったのですが、その人は坊主頭で全裸の、痣と皺だらけで腰が曲がった老人のような見た目でした。扱われ方からして、多分あの人が『ストーカー』と呼ばれていた人なんだと思います」
ついに我々調査隊の中で、今まで疑惑に過ぎなかったものが確信に変わった。「家族の会」は、人々を洗脳し、老人虐待や実子の監禁という異常な行為を強いる、明白な反社会的カルト集団だったのだ!
「その後私たちはすぐ、このことを警察に通報しました。警察は、実は『家族の会』に関する同様の通報を同時期に何度か受け取っていたようで、後日対面で詳しく事情を話すことになりました。その時、担当の刑事さんは、加奈のことで私たちを不安にさせて申し訳なかったと言って、何度も何度も頭を下げてきました。でも、私たちの方も申し訳ない思いでいっぱいでした。『家族の会』のことでこんなことになったのは、私たちが警察を信じられなかったせいなのに。とにかく、警察の準備が整い次第あの施設に強制捜査を行うことを明かしてくれて、ようやく安心したのを覚えています。……しかし、後から聞いた話では、『家族の会』は事前にこれを察知して『きょうだいのお納め』を中断し、その痕跡を完全に隠していたようで、警察の強制捜査もむなしくこの事件は立件できなかったそうです。あのお爺さんも、どこか別の場所に移していたんでしょうかね。
私たちはその後すぐに家を引っ越しました。もしかしたら、この家でずっと待っていれば、加奈はいつか何事もなかったようにひょっこり帰って来るんじゃないか、なんて思うこともありました。でも、最初に近所のカフェで『家族の会』の人と接触した時点で、私たちはみすみす家の場所まで教えてしまっていたんです。あの人たちが今にも家に押しかけてくるんじゃないかと思うと、怖くて仕方がありませんでした。だから、加奈のことを思うと辛かったけど、こうして今いる場所に引っ越してきたんです。加奈だって、帰って来るなら、安心できる場所がいいだろうから。それからは何事もなく……加奈は、まだ帰ってきていないけど。それでも、ここで理央が生まれて、元気に育ってくれました。私も夫も、今の暮らしがあるのは理央のおかげだと思っています」
谷氏のあたたかい目線が、隣の部屋で遊んでいる理央くんに向かった。
「理央が産まれることになったとき、実は、少し怖かったんです。もちろんとっても嬉しかったし、幸せでしたよ。だけど、また同じことが……加奈と同じことが起こってしまったらどうしよう、っていう考えが、頭から離れないんです。お医者さんの話を聞いている時も、お腹に加奈がいた時のことがフラッシュバックして、その時の私は、もちろん不安もあったけど、本当に幸せで……。そう考えた時、もうすぐ理央のお母さんになるのに、こんな暗い気持ちになっているなんて、母親失格なんじゃないか、とさえ思えてしまって。だけど……夫がしっかり私の手を握ってくれて、ようやく産まれた小さな理央が、がんばって、がんばって、初めて泣き声を上げたあの瞬間、そんなうじうじした気持ちは吹き飛びました。私が、私たち二人が、絶対に理央を守るんだ、そう心に誓ったんです。
それから理央は何事もなくすくすくと育っていきました。本を読むのが好きなところは、きっと加奈に似たんでしょうね。……理央が笑ってくれるおかげで、私と夫にもようやく本当の笑顔が戻ってきたんだと思います。最初は、加奈が見つからないまま、私たちだけが幸せになるなんてできない、許せないと思っていたけど、理央の前ではそんなこと言ってられませんよね。理央を不幸にさせてしまったら、お姉ちゃんの加奈にも顔向けできないですよ。だけど、理央が元気で、本当によく笑う明るい子だから、私たちが理央を幸せにするっていうより、むしろ理央のおかげで私たちが幸せになっているっていう方が正しいかな(笑)。今年の春からは小学校に入って、ちょっと反抗期になってますけど(笑)」
谷一家は、息子のおかげで悲劇に負けなかったのだ――調査隊は今月のページをそう締めくくるはずだった。取材の終わり際、突如としてインターホンの音が響くまでは。
「ハマナソウキチくんをご存じですか」
インターホンの後にかすかに玄関外から聞こえてきたのは、しわがれた老人の声だった。取材班と谷氏は息を呑み、無言で目を見合わせた。前回の北口氏への取材時にかかってきた電話と、あまりにも特徴が一致している。数秒の沈黙の後、気の抜けたインターホンの音が連続で何回も、暴力的に鳴らされ始めた。隣の部屋にいた理央くんは泣き出し、谷氏のもとへ駆け寄ってきた。谷氏は理央くんを固く抱き締めながら、目を見開いて震える。しばらくして、インターホンの音が止んだ後、我々がドアスコープを確認した時には既に訪問者の姿は無かった。我々調査隊の背筋に寒いものが走った。この悲劇は、まだ終わっていないかもしれない。
我々はすぐさまこの件を警察に通報したが、実害が発生していないためか、電話口での対応で済まされてしまった。理央くんが泣き疲れてリビングで眠ってしまった後、谷氏は我々にこう語った。
「……今思い出したんですが、あの『ハマナ』という名字……。施設に行った時聞かされたんですが、確か、『家族の会』の代表の名前は、『浜名亜実』でした。だから、『ハマナソウキチ』はもしかしたら……あの人の誘拐された子供だったかもしれません」
凶悪なカルト団体「家族の会」の脅威は今なお続いているのか? 施設で虐待を受けていた「ストーカー」と呼ばれる老人と、我々の行く先に度々現れる「ハマナソウキチ」を捜す老人……彼らは何者なのか? 我々は危険を顧みず調査を続行する。有力な情報を持ち、我々と共に真相を探りたいと思う者は、すぐさま月刊テンポ・ルバート編集部オカルト係に問い合わせてほしい。それでは読者諸君、次号の「となりのオカルト調査隊」でまた会おう。
青梅市カルト児童集団監禁事件捜査資料:施設居住空間から発見された日記(1999年分から抜粋)
あのストーカーは私たち誘拐被害児童の家族の気持ちを踏みにじる最低の存在だ。あいつは宗吉くんの無事を祈って日々神経をすり減らしている浜名さんをターゲットにしてつきまとい、おちょくって楽しんでいる。しかもあいつはつい先日から、施設の周辺までうろつき始めるようになった。どうやら私たちが出した生ごみを漁ったりもしているらしい。本当に神経を疑うし、気が違っているんだろう。警察に相談しても全く役に立たない。アメリカやヨーロッパではストーカーを裁けるようになったのに、日本はいつも遅れている。浜名さんはいよいよ我慢の限界に達したようで、あいつを監禁して痛い目を見せてやろうと言っている。正直、施設の建物の中にあいつが入ってくることになると考えると吐き気がするほど嫌悪感があるが、浜名さんはそれが気にならないくらいあいつに激怒しているようだ。でも確かに、何度言ってもつきまとうのを止めないのだから、いっそのこといたぶって分からせるしか無いのかもしれない。自業自得だ。二度とここに近づこうだなんて思えないようにしてやる。
月刊テンポ・ルバート2014年8月号掲載「『教祖』は口のきけない女? 善良な団体を乗っ取った洗脳術」
我々は今、9年前に解散した危険なカルト団体「関東地方誘拐被害児童の家族の会」を追っている。その中でコンタクトをとることに成功したのが、この「家族の会」がカルトに変貌していった過程を知るという人物、埼玉県在住の酒井正氏(55歳男性・仮名)である。彼は幼い時に兄を誘拐された過去を持ち、さらに彼の父親は以前「家族の会」の代表を務めていたというのだ。酒井氏は我々の取材に快く応じてくれた。
「……もともと『家族の会』は、子供を誘拐された家族が協力して支え合う、心の拠り所となる場所でした。人を傷つけ、洗脳するようなカルト集団では、断じてありませんでした」
埼玉県のあるカフェで、酒井氏はこう切り出した。彼は独り身で、肉親はいない。彼の人生は、兄の誘拐事件によって、決定的に変えられてしまったのだという。
「正直、あの時俺は物心がついて間もないころだったから、兄貴の顔もぼんやりとしか覚えていないんです。だけど、兄貴が帰ってこなかった夜のことは鮮明に覚えています。夜七時、晩御飯の時間には、父は兄貴が帰ってきたらうんと叱ってやるんだと言っていました。俺も兄貴も小学生だったけど、兄貴はよくその辺を悪い友達とほっつき歩いていたんです。だけど、それが八時、九時となるにつれ、父も母も落ち着かない様子になってきて、警察に電話する、しないの口論を始めました。俺は何が何だか分からなかったけど、兄貴がいないという異常事態の中で、父と母の明らかに普段と違う、切羽詰まった雰囲気が恐ろしくて、不安になったのを覚えています。子供の目には、大好きな家族が突然別物になってしまったように感じられて、そして……。その日を境に、俺の家族が元に戻ることはありませんでした。
一週間経っても、兄貴は見つかりませんでした。あのとき兄貴が自力で移動できた範囲は徹底的に捜索されましたが、何の成果もなく、警察はこの失踪を誘拐事件として結論づけました。学校に行くと、最初の内はみんな兄貴の噂話に夢中でしたが、一か月が経つ頃には普段の調子に戻ってマンガやゲームの会話をしていました。だけど、俺の家族が普段通りに戻ることはありません。兄貴は一年経っても見つからず、父と母は毎晩のように喧嘩していました。なのに、二人とも俺の前では無理して明るく振る舞っていて……ひどい話かもしれませんが、幼い俺には、すごく不気味に思えました。……それからさらに半年ほど経った後、母は、家で首を吊って、自殺しました。通夜の時、父は俺を抱き締めて泣きました。父は無骨な感じの人で、こんなに感情をあらわにするところは見たことが無かったから、驚きましたよ。でもあの時、俺はやけに冷静に母の死を受け止めていて、泣いたりもしませんでした。日ごろのストレスで少しおかしくなっていたんだと思います。
ともかく、父がその後入会したのが、あの『家族の会』だったんです。父はよく俺を連れて、『家族の会』の施設に行きました。そこには俺たちと同じような境遇の人がいて、俺と同じようにきょうだいを誘拐された子供もいました。あの人たちは、俺たちの話を聞いて、真心を込めて励ましてくれました。生活のための援助を貰うこともしばしばありました。俺は、『家族の会』の人に、手を強く、温かく握ってもらったとき、兄貴が誘拐されてから初めて、ようやく涙を流しました。……父と俺は、『家族の会』のおかげで再び前を向けるようになったと思います。母と一緒にここに来ていれば、俺たちの未来はまた違っていたかもしれません。とにかく、あの時点の『家族の会』は、健全で素晴らしい団体でした。虐待まがいの異常な行為なんて、どこにもなかったんです」
酒井氏が語る「家族の会」の姿は、我々が今まで調査してきたものと全く異なるものだった。
「兄貴が見つからないまま、あっという間に十年が経ち、俺は上京して就職しました。たまに帰省しても、父と兄貴の話をすることはほとんど無くなりました。ただ、父はその後も『家族の会』で熱心に活動し続けたようで、俺が三十になるころには、五代目として『家族の会』代表の座をその先代が建てた施設ごと継ぎました。そうだ、あなた方の記事の中で『別館』というものが出てきていましたが、当時はそんなものはなかったはずです。とまあ、それで、その数年後久しぶりに施設に行ってみると、父は気づけば多くの人に慕われるようになっていました。『自分の家族に起こった悲劇を繰り返してほしくない』と、口癖のように言っていましたよ。……しかし、あの時既に、あの女は……浜名亜実は、『家族の会』に潜んでいたんです」
「浜名亜実」……北口氏と谷氏がともに言及した、後に「家族の会」の代表になる女だ。「家族の会」の変貌には、この女が関わっているのだろうか?
「全てのきっかけは、あの日、父にかかってきた一本の電話でした。……警察が、兄貴の遺体を発見したんです。どうやら、兄貴を誘拐して殺した男が、寿命で死ぬ間際になって犯行を自白したらしく、その男の証言の通りにある山のふもとを掘り返してみると、骨になった兄貴が見つかったということでした。兄貴がいなくなってから、三十数年が経っていました。……父は、絶望的だと分かっていてもなお、兄貴が生きていると信じたかったんでしょう。だから、その望みが打ち砕かれて、茫然としているように見えました。そんな自分を負い目に感じてしまったのか、父は次第に『家族の会』とは距離をとって、一人で家にいることが増えるようになりました。そしてついに、15年前、父は代表を降りて、浜名亜実を正式な六代目代表に任命したんです。
浜名亜実は、生まれつき耳が聞こえず、言葉を話すこともできなかったそうです。結婚して、長男を産むも、その後すぐに夫の不倫が原因で離婚し、そのうえ13歳の誕生日の直前で一人息子の宗吉くんを誘拐されて……彼女の人生は辛いものだったでしょう。人と比べるようなものではないでしょうが、彼女の息子を思う気持ちは、尋常なものではなかったようです。一種の依存だったんでしょう、あの人は、自分の全てを捧げてでも、息子を取り戻したいと願っていたんです。それでも、彼女にはどこか理知的な魅力があって、他の被害者家族たちと毎日のように文通を交わし、根気強く励ます優しい人だったそうです。代表になる前から、子供の好きだったものを持ってきて共有する取り組み……後の、取材を受けたみなさんがおっしゃっていた儀式……『跡奉』の原型でしょう。そういうことを始めたりと、積極的に『家族の会』で親睦を深めていました。俺が最初に見たときには、まだ『跡奉』の個室が置かれていないあの部屋で、親たちは輪になっておもちゃやサッカーボールを持ってきて、自分の子供の話に花を咲かせていました。被害児童のきょうだいもちらほら見ましたが、あの時には泣いている子供なんて一人もいませんでした。
一方父は、代表を降りてからみるみるうちに衰弱し、ついに肺癌が見つかって入院していました。面会に行くと、父はやはり『家族の会』のことを気にしているようで、『浜名さんがいるから心配ないと思うが、家族の会の人たちを気にかけていてくれないか』としつこく言ってきました。だから、父を安心させるために、俺はあの施設に行ったんです。浜名亜実が代表になって、半年ほど経った頃でした……。その時にはすでに、『家族の会』はおかしくなっていたんです」
谷氏の考えの通り、「ハマナソウキチ」は「家族の会」の代表・浜名亜実の誘拐された息子で間違いないようだ。浜名亜実は、いかにしてカルト団体を作り上げたのだろうか?
「最初に奇妙に思ったのは、施設を訪れてすぐ、見知った会員の人たちと挨拶をしている時でした。普段は応接室として使われていた大きなテーブルが置かれている部屋に、布団がたくさん敷かれていたんです。聞いてみると、最近は皆毎日この施設で寝泊まりするようになったのだと言われました。父が施設を管理しているときはいつも夜には施錠していて、宿泊するなんていう話は聞いたことはなかったし、わざわざ家ではなくこの施設で生活する意味は一体何なのかと、不審に思いました。とはいえ、会員が施設に宿泊しているくらいのことで『家族の会』がおかしくなってしまったとまでは思いませんでした。それを確信したのは、あの『跡奉』の部屋に行こうとした時です。……部屋の内側から、子供が『出して』と言って泣く声と、ドアを叩く音がするんです。ドアはこちら側から鍵がかかっていました。俺は何事かと思ってすぐにドアを開けようとしたんですが、その瞬間、腕をつかまれて制止されました。振り向くと、そこにいたのは浜名亜実でした。あいつは携帯していたホワイトボードに訳の分からないことを書きなぐってきました。確か……『ごめんなさい、跡奉のために部屋には鍵をかけています。気にしないで』と。あの『跡奉』という意味の分からない言葉は、ずっと記憶にこびりついていたんですが……。まさかここからさらに恐ろしい儀式が発展していたとは、あなた方の雑誌記事を読んで初めて知りました。
あのドアには蔦のような装飾が付いた磨りガラスがはめ込まれていて、装飾部分は普通のガラスになっていたから、俺はそれ越しに中の様子を伺おうとしました。あまりよく見えませんでしたが、中には子供が十何人かいるらしく、見覚えがあるような子供もちらほらいました……被害児童のきょうだいです。床には、親たちが持ってきた被害児童のおもちゃ等が散乱していました。ガラスに張り付いて目を凝らしていると、突然、ドアの向こうから手のひらが叩きつけられてきました。しゃがんでドアに近づいていたので、その人の顔や背格好は見えなかったのですが、磨りガラス越しにも、その人が裸で、腕には深い皺が刻み込まれていることが分かりました。間違いなく、記事にあったあの『ストーカー』です。俺は悲鳴をあげて振り向き、会員の人たちの方を見ましたが、誰もこの異常な事態を疑問にも思っていないようでした。……子供の泣き声が響く中、俺はめまいがして、動悸が止まりませんでした。あの時と同じでした。俺の家族と同じように、俺の知る『家族の会』は、別物になってしまったんです」
あの恐ろしい「跡奉」の儀式は、ここから始まったのだ。我々はこれまでに様々なカルト組織への潜入取材企画を行ってきたが、「修行」などと称して閉鎖空間の中で共に寝泊まりし、メンバーの生活や意思をコントロールすることは、洗脳の第一歩であり常套手段である。浜名亜実の狙いはそこにあったのではないだろうか。
「施設から逃げ出した俺は、このことを父に伝えられませんでした。……父にとって『家族の会』は、新しい家族のようなものだったんだと思います。老いて弱った父には、せめて幸福な家庭の中で余生を過ごさせてやりたかったんです……たとえその幸福な家庭が、最早父の頭の中にしか無かったとしても。結局、数年後に父は癌が全身に転移してあっさり死にました。それ以来俺は、『家族の会』に関わっていません。変わってしまった、変えられてしまった『家族の会』を詮索しても、俺には辛いだけでしたから。……俺は、あの会にもう関わりたくないという一心で、全てを見なかったことにしたんです。でも、今では、そうやって逃げたせいであのカルトがさらに多くの悲劇を生むのを許してしまったのかもしれないという後悔でいっぱいです。今更どうしようもないかもしれませんが、せめて俺の言葉が何かを究明する助けになってほしいと願います」
取材を終え、酒井氏と別れた調査隊はカフェを出た。このとき、調査隊の編集者の一人は、交差点の人ごみの奥に佇み、こちらを凝視している背高の異様な老人男性を目撃したという。この老人はただの通行人だったのだろうか? 「家族の会」の謎が紐解かれるにつれ、我々につきまとい浜名宗吉くんを捜す老人の謎は深まる一方だ。彼は施設に監禁されていた「ストーカー」であり、宗吉くんを使って浜名亜実への復讐をしようとしているのだろうか? 些細な事でも、何か情報を持っているという者は、月刊テンポ・ルバート編集部オカルト係に問い合わせてほしい。それでは読者諸君、次号の「となりのオカルト調査隊」でまた会おう。
月刊テンポ・ルバート2014年9月号掲載「洗脳された両親に監禁された少女……彼女を助けた老人の衝撃的な正体!」
あらゆるコネクションを通じて「関東地方誘拐被害児童の家族の会」の調査を進めている中、調査隊は一通のメールを受け取った。送り主は栃木県在住の稲田瞳氏(21歳女性・仮名)であり、彼女はなんと幼少期にあの「きょうだいのお納め」と呼ばれていた行為の被害者となって「家族の会」の施設に監禁されていたことがあるというのだ。我々はすぐさま取材を取り付け、彼女の自宅へ向かった。
「15年も前のことで、しかも私は当時6歳くらいだったから、記憶があやふやだったり、そもそも勘違いだったりすることがあるかもしれないんですけど。まあ、とにかく、あの『家族の会』について覚えている限りの全てを話そうと思います」
先月号で話を伺った酒井氏が最後に「家族の会」の施設を訪問したのは14年半前のことだった。つまり、稲田氏はその半年前、浜名亜実が「家族の会」の代表になったのとちょうど同時期にあの施設にいたという事になる。稲田氏は、ただおもちゃが持ち寄られていただけの部屋が、子供たちを閉じ込める「跡奉」の部屋になった経緯を知っているのだろうか? あるいは、その中にいた「ストーカー」と呼ばれる謎の老人を見たのだろうか? 我々は居住まいを正して取材を始めた。
「私には二つ上の姉がいました。姉は、私に物心がついてすぐくらいのときに誘拐されました。だから、私は姉のことをあまり覚えていません。私の中の記憶がはっきりとしてくるのは、姉がいなくなった後、両親が私を連れて車で遠くまで行くことが増えた頃です。目的地は、昔はもちろん知らなかったんですけど、『家族の会』の施設です。車を降りると青い三角屋根の綺麗なお家があって、その中で同年代くらいの子供とたくさん遊んでいた覚えがあります。両親が入会した当初は、まだ『家族の会』はカルトになっていなかったんだと思います。むしろ、遊ぶ友達もいるし、おもちゃもたくさんあるしで、私は当時、あの施設に行くのを楽しみにしていました。
『家族の会』がおかしくなっていった経緯は、ぼんやりと覚えています。まずは、あのおもちゃの部屋……皆さんが記事で言っていた、『跡奉』の部屋だと思います。もともと私たち子供はあの部屋でよく遊んでいたんですが、ある時中の物が全部他の場所に移されて、私たちは入るのが禁止になりました。代わりに、あの部屋には外側から鍵がかかって、『ストーカー』と呼ばれていた人を閉じ込めるのに使われ始めたんです。大人たちは毎日あの部屋に入っては大声を上げて、多分暴力を振るっていました。両親に聞いてみると、『あの人はとても悪い人だから、みんなで懲らしめている』んだと言っていました。最初は怖かったけど、そのうちそれが自然になっていって、次第に子供たちもみんな気にしなくなりました。
それから少し経った頃、いつも通り施設で他の子たちと遊んでいると、気づいたら大人たちが玄関に集まっていて、何か嬉しそうに興奮していたことがありました。聞いてみると、さっき誰かが施設に来て、誘拐された子供の取り戻し方を教えてくれたというんです。私はなんだか不思議に思いながらも、姉が帰って来るのが楽しみになった覚えがあります。その夜、普段だったらもうとっくに帰る時間になっても、大人たちはなぜかそれに気づいていないようにおしゃべりを続けていました。私は正直ラッキーと思ってその後も一時間くらい遊んでいたんですけど、さすがに疲れてしまったし、どんどん不安になってきて、両親に『帰らないの?』と尋ねたんです。……すると両親は笑って、『これからは皆でここに住む』と言ってきたんです。私はよく分からないまま、その日はそのまま施設で寝てしまいました。そして、その次の朝、目が覚めると私たち子供は皆、あの『ストーカー』と同じ部屋の中で閉じ込められていたんです」
やはり「家族の会」がカルト集団に変化していった背景には、あの「ストーカー」の存在が大きく関わっているようだ。さらに、施設に来て「子供の取り戻し方」を教えたという謎の人物も重要な鍵を握っているに違いない。あの訪問の直後に子供たちを監禁する「きょうだいのお納め」が始まったということは、誘拐された子供のためだとして「家族の会」で行われていたあの恐ろしい儀式や行為の大本は、全てここで教わった「子供の取り戻し方」だったのではないだろうか?
「私も他の子供たちも、皆パニックになって泣いてしまいました。『ここから出して』と叫んでも、鍵を開けてくれる気配は全くありません。それに、あの『ストーカー』と呼ばれていた人が、ドアの目の前で縄で縛られて固定されたままこっちを見ていたんです。髪は無く、体は全裸で皺と痣だらけで、子供たちは皆初めて直に見るあの人に怯えてドアに近づけませんでした。泣き疲れてふと気づくと、部屋には他の場所に持って行かれたはずの、おもちゃや服などの誘拐された子供の物が戻されていました。しかも、何だかそういう子供の物は倍増しているようで、子供用の箸や食器までその辺の床に置かれていました。……しばらくすると大人が一人部屋に入ってきて、私たちに朝ごはんをくれました。『そんなのいいからここから出して』と言うと、その大人は優しげな口調で、『皆は誘拐されたきょうだいを助けるためにお納めされている』『置いてある物や皆が奪われたりしないように鍵をかけないといけない』『あのストーカーは別館が完成し次第そこに移すから、少しの間辛抱してほしい』みたいなことを言ってきました。
私たちが何も言えずにいると、その大人は今度はあの『ストーカー』のところに行って、ものすごい剣幕であの人のことを罵り始めました。あの人に生ごみの袋を投げつけて、『二度とここに近づかないと誓うまで拷問し続ける』とか『そんなに生ごみが食べたいなら一生食べていろ』とかいうようなことを言っていました。その人が部屋を出ていった後、私たちは泣きながら、無言で朝ご飯を食べました。……それから一年ほど、私はあの部屋の中で生活しました。先月号で取材を受けていた人が施設に来たのが、この頃のはずです。ご飯は大人たちが毎食持ってきてくれて、トイレ用のバケツも毎日交換してくれました。お風呂の代わりに濡れタオルで体を拭きました。大人たちはたまに大勢で詰めかけて、『ストーカー』に暴力を振るっていました。その中には時々私の両親もいました。血が飛び散るほどの暴力で、私たちはその度に息を殺してそれが終わるのを待っていました。『ストーカー』は叫んだり呻いたりはしていたけど、大人たちに何か言われても一言も喋りませんでした。耐えられなくなった子供が、大人が部屋に入って来るタイミングで脱走することもしばしばあったけど、みんな結局は部屋に連れ戻されてしまいました。
当時は時間の感覚も無くなっていたんですけど、多分閉じ込められて半年後くらいから、私は『ストーカー』がかわいそうになってご飯を少し分けてあげるようになったんです。最初はもちろん怖かったけど、どれだけ近づいても危害を加えてくるような素振りは全然なかったから、途中からは何か親近感のようなものも湧いてきていました。ただ、勇気を出して話しかけても、あの人が何か喋ることはありませんでした。……近くでよく見ると、『ストーカー』の体は本当に痛々しく傷ついていました。でもそれ以上に、何と言うか、不思議な点が多かったんです。私は最初、あの人をお爺さんだと思っていました。『オカルト調査隊』さんの取材の中でも、あの『ストーカー』を遠くからだったり磨りガラス越しに見ていた人は、あの人を老人だと思っていたはずです。でも、あの人はいつも髪を無理やり抜かれたり切られたりしていたせいで禿げ上がって見えていただけで、実際は黒い髪がちゃんと生えてきていました。痛めつけられた時の叫び声も、顔の形も、今思えばむしろ幼いような感じだったし、それに体中にある皺も向きが不自然で……まあ、これに関しては、後で話します。とにかく、私はある時思い付いて、部屋で見つけた柄付きの女の子用のメモ帳とかわいいペンを使って、あの人と筆談をしてみようとしたんです。そして、あの人はそれに応えてくれました」
「ストーカー」の謎は深まるばかりだ。稲田氏と「ストーカー」の接触はどのようなものだったのだろうか? 稲田氏はどこか懐かしむような語り口で続ける。
「確か、拙い字で、『わたしはいなだひとみです。あなたはだれですか?』みたいなことを書いて渡したと思います。するとあの人は、『ぼくは はまなそうきち です』と書いて、返してきました。平仮名だったのは多分、私に配慮してくれたんだと思います。当時は知らなかったんですが、あれは間違いなく、記事の中で言及されていた浜名亜実の息子の名前でした。宗吉さんは母からの遺伝で生まれつき耳が聞こえず、手話か筆談でしか喋れないんだそうで、それから私たちは筆談でいろいろなことを話すようになりました。その中で、私は宗吉さんになぜ『ストーカー』と呼ばれ、こんなひどいいじめを受けているのか聞いたことがあります。帰ってきた答えは、当時の私には……今の私にとっても、信じられないようなものでした。まず、宗吉さんは学校からの帰り道で何者かに誘拐されて、気づいたら知らない家にいたそうです。けど、どうにかそこから逃げ出すことに成功して、自力で自分の家に帰ってきたというんです。でもそこで待っていた母親は、帰ってきた宗吉さんを偽者だと思った。激高して、宗吉さんを手話で罵って、追い返したんです。宗吉さんはこの文章を書きながら泣いていました。宗吉さんは、まるで訳が分からなかったそうです。何度自分は偽者ではないと訴えても、母親はますます怒って『二度と来るな』と言うばかりでした。その後数日間は行く当てもないから家の敷地の隅に座りこんで、お腹がすいたら家の前に捨てられていたごみを漁ったそうです。転機になったのは、ある日この施設を見つけたことでした。家が施設の近所で、母親の車を追ってたどり着いたらしいです。最初はここに居る別の大人なら助けてくれるかもしれないと思ったらしいんですが……。結局あの人たちも同じように、宗吉さんを睨んで、宗吉さんには聞こえない暴言を吐いて、門前払いにしてしまったそうです。それでも行く当てがないから、うつろに駐車場に座って過ごしていたら、ついにある時、この部屋に監禁されて、激しい暴行を受けるようになったんだといいます。
筆談するようになってから数か月後、宗吉さんは私を施設から脱出させる計画を立ててくれました。最初に来た大人が言っていた『別館』が完成したみたいで、宗吉さんが近いうちにそこに移されることになっていたんです。私たち子供の世話をする大人たちは、『あのストーカーは一生暗くて狭いところに閉じ込めておくから安心して』みたいなことを言っていました。計画といってもシンプルで、部屋から出されるタイミングで宗吉さんが暴れて、囮になるというだけのものでした。一緒に逃げたいと言ったけど、断られました。最後に宗吉さんは、誘拐されてから優しくしてくれたのは私だけだったと言ってくれたような気がします。それからあのメモ帳とペンは、宗吉さんが持っていくことになりました。……脱出した日のことは、正直、何も覚えていません。まるで悪夢から覚めたように、私は気づいたら伯母さんの家で暮らすことになっていました。あの後『家族の会』は強制捜査を受けたらしいんですが、児童虐待の十分な証拠は見つからず、結局何も事件にはならなかったそうです。私の証言も多分、ほとんどは子供なりの勘違いや妄想だと思われたみたいでした。正直、自分が体験したのが本当のことなのか、もう私にも確信はできません。両親に私をきちんと育てる意思がなかったことだけは事実のようで、それから私は子供のいなかった伯母さんの家で可愛がられて育ちました」
稲田氏の話は、あまりにも衝撃的だった。「ストーカー」は浜名宗吉くんその人で、幼い稲田氏を「家族の会」から救い出したというのだ!
「私はそれからずっと、精神的に不安定な状態が続いていました。あの『ストーカー』……宗吉さんは、極限状態だった私が生み出した妄想なんじゃないか。あの施設に閉じ込められていた間の記憶も、子供らしい何かの勘違いだったんじゃないか。って、私の人生のいったいどこからどこまでが本物なのか、分からなくなってしまったんです。両親や姉とどんな暮らしをしていたのかも、何もかも。そうして頭の中がごちゃごちゃして、泣きたくなった時、私はいつもカッターで手首を切りました。中高生くらいの時です。伯母さんは泣きながら、『そんなことはやめて』って言ってきました。だけど私はそれを繰り返して、手首には何重にもリストカットの傷跡がつきました。今では手術を受けて、見えづらいようにしているんですが……。あれを見た時、私はふと、宗吉さんを思い出したんです。指の節から目尻まで、あの人の体全身に刻まれていた、近くで見るとどこか不自然な皺が、なぜだかありありと記憶の中で蘇ってきたんです。
私の記憶が夢か幻じゃないのなら、あの皺に見えていたものは多分、全身をくまなくカッターで切られてできた傷跡だったんだと思います」
稲田氏がそう言い終わらないうちに、激しいノックの音とインターホンのチャイムが部屋に響き渡った。あの、しわがれた老人の声がした。
「ハマナソウキチくんをご存じなのですか。話を聞かせてください。ハマナソウキチくんはどこですか。家から出てきてください」
稲田氏と我々調査隊は戦慄した。ノックは数分間続いたが、物音がはたと止み、我々がドアスコープを覗いた時には、玄関の前にはもう誰もいなくなっていた。警察には再びすぐにこの老人の件を通報したが、やはりこれだけで警察が動くのは難しいという。「ストーカー」が稲田氏の言う通りの人物なのだとすれば、この老人が「ストーカー」と同一人物であるはずがない。ならばこの老人はいったい何者なのか? どうやって我々調査隊の行く先々に現れているのか? 老人の謎、そして「家族の会」の全ての謎に迫るべく、我々は引き続き調査に努める。来月号は、驚くべき人物へのインタビューが紙幅を増量して掲載される予定だ。その人物とは、何を隠そう、浜名亜実その人である。さて、毎度のことだが、「家族の会」に関して何か情報を持っている者がいればぜひとも月刊テンポ・ルバート編集部オカルト係に問い合わせてほしい。それでは読者諸君、次号の「となりのオカルト調査隊」でまた会おう。
月刊テンポ・ルバート2014年10月号掲載「紙面増量! カルトの代表が自供した真実! 像を結ぶ悲劇の黒幕」
誘拐児童を取り戻すための儀式と謳って数年にわたり児童を監禁・虐待し続けた後、9年前に忽然と姿を消した狂気のカルト団体「関東地方誘拐被害児童の家族の会」。我々調査隊はここまで約半年間にわたってこの団体を調査し、闇に葬られようとしていたその姿を浮き彫りにしてきた。今回我々が紙面を増量して取材を行うのは、元々善良な組織だった「家族の会」を恐ろしいカルト団体に作り変えた張本人、浜名亜実氏(42歳女性)である。彼女はなんと、自ら我々に取材を受けることを申し入れてきたのだ。
「私はこの9年間、自分が『家族の会』で行ったことから目を背け続けてきました。しかし先日、私らしき人物が言及されていると知人に教えてもらい、そちらの記事を読ませていただいてから、あれは本当に私がやった、現実で起こった出来事なんだということを再確認して、恐ろしくなりました。こんなことをしておいて、全てを忘れてのうのうと暮らすことなんてできません。私は罪を償わなければなりません。そうでないと、宗吉に会わせる顔が無いんです。だから私は、ここで私の知る限りの全てのことを話してから、警察に出頭しようと思います」
我々は彼女が現在一人で暮らしているという静岡県の住居に招かれた。調査で得た情報の通り、浜名氏は生まれつき聴覚に障害を持っており喋って会話することができない。そのため、取材はモニター上にキーボードで交互に文章を打ち込んで行った。身構える我々を前に、浜名氏はそっとキーボードを叩き、『家族の会』との出会いを語り始めた。
「宗吉は、私が生きる理由でした。夫とは離婚し、両親とは既に死別していたから、私は誰にも頼れないまま一人で宗吉を育てました。日常生活はいろいろ大変で、つらいことも多かったです。しかし、宗吉はろう学校で友達をいっぱい作って、家に帰ってきたらいつもその日あったことを手話でたくさん教えてくれました。そうやって楽しそうに生きている宗吉を見るだけで、私は本当に救われたような気持ちになりました。親としては間違っていると思うけど、私は宗吉に依存していたんだと思います。でも、そうなってしまうくらい、私には支えになる人がいなかったんです。世界の中で、宗吉だけが私の味方だったんです。だから、宗吉が誘拐されて、いなくなってしまった時、」
浜名氏の手が一瞬止まった。続く言葉を言い淀んだ、と言うべきだろうか。
「自殺しようと思ったんです。職場にも行けなくなって、家であの子の帰りを待ちながらずっと、このまま宗吉と会えないのなら死んだ方が良いと考えていました。一か月経っても宗吉が帰ってこなかったら、首を吊ろうと決めました。食事もしないで玄関でぼんやり座ったまま、気づいたら朝になっていることもよくありました。宗吉が帰って来るのを待っているのか、一か月経って楽になれるのを待っているのか、私にはもう分かりませんでした。そんなある日、宗吉の担任の先生が家に来たことがありました。先生は私のことを心配してくれていたようで、私には何か居場所が必要だと繰り返し言いました。当事者として、耳の聞こえない私たちが社会的に孤立しがちなことには敏感だったんでしょう。それで先生が見つけてくれたのが、あの『家族の会』だったんです。私は流されるまま『家族の会』の施設に連れて行ってもらいました。
『家族の会』の人たちは、喋れない私に最初は不慣れな様子であたふたしていましたが、それでも私と真摯に向き合ってくれました。特に当時代表をされていた方は、何度も根気強く私に話しかけ、子供が帰ってくるという希望を捨てずに待ち続けることが大事だと励ましてくれました。奥さんを自殺で亡くしていたあの人は、多分私にその時と同じような危うさを感じ取っていたんでしょう。施設は近所にあったから、それから私は何度も『家族の会』に通うようになりました。『家族の会』の人たちと交流する中で私の孤独感は次第に薄れていき、自殺を考えることもなくなりました。仕事にも復帰して、きちんと生活を送れるくらいに回復したんです。そして、正式に入会してからは、宗吉の帰りを待ちながらも、助けられるばかりではなく自分から周りの被害者家族を助けていきたいと思うようになりました。私がやってもらったことを、他の人にもしてあげたかったんです。おもちゃを持ってきて、自分の子供との思い出を語るというイベントをやるようになったのも、その頃です。そして、入会してから数年後、そちらで取材されていた記事にあった通りの経緯で、私は『家族の会』の新しい代表を務めることになりました」
浜名氏は、素晴らしい団体だった頃の「家族の会」に救われた一人だったのだ。そんな彼女が、一体なぜ「家族の会」をカルトに変えてしまったのだろうか?
「代表になってすぐのことでした。家に知らない人が来たんです。最初に来た時は、チャイムが、と言ってもフラッシュチャイムですが、それが光ったからドアを開けに行ったら、その知らない人は泣きながらいきなり私に抱き着こうとしてきました。びっくりして振り払うと、その人は驚いたようにして、手話で『お母さん、どうしたの』と言ってきました。私が立ち尽くしていると、あの人は続けて、『宗吉だよ。帰ってきたよ』と言ってきたんです。一応言っておきますが、あの人はどう見ても、明らかに宗吉ではありませんでした。今でも確信を持って言えます。何故だか知りませんが、あの人は宗吉を自称して、私に嫌がらせをしてきたんです。私は頭に血が上って、すぐにあの人を追い返しました。しかし、あの人はそれから数日間、昼夜を問わず何度も同じように家に押しかけてくるようになりました。『言いつけを破って暗い道から帰ってごめんなさい』とか、『許してください。家に入れてください』とかいう風に、あの人は本当に自分が宗吉であるかのように振る舞い続けました。あまりにも神経を逆なでするものだから、私は堪えられなくなって。施設で『家族の会』の人たちにこのことを相談しました。その結果、警察に通報することになり、電話であのストーカーのことを伝えてもらったのですが、警察は実害がないなら対処できないとの一点張りだったみたいです。
その後、あの人は『家族の会』の施設にまで後をつけてきました。何度『出ていけ』と伝えても、あの人は駐車場のあたりをうろついて、他の被害者家族にも迷惑をかけるようになったんです。私は最初、あの人をただ追い払いたいと思っていましたが、こうして怒りが膨らんでいくにつれて、それだけでは足りないと思うようになりました。宗吉という私の一番の宝物を、私の全てを侮辱したあの人には、永遠に責め苦を与え続けなければいけないと思ったんです。そしてある時、ついに『家族の会』で、あの人を閉じ込めて拷問することを提案したんです」
浜名氏の表情がこわばる。
「あの人のストーキング行為は非常に悪質で、今でも許せないと思っています。しかし、それでも、監禁して拷問するなんていうのは、常軌を逸したありえないことのはずです。今でも自分がこんなことを提案して、そして実際にやってのけたというのは、あまり信じられません。怒りのあまり理性が無くなっていたとしても、普通に生きてきた一般人がこんなことをしようと思うものでしょうか? しかし、それでも、私は、間違いなくそれをやったんです。『家族の会』でもあの提案に反対した人はいませんでした。あの人を永遠に監禁し苦しめたかった私とは違って、他の人達はあの人を痛めつけて二度とこの施設に近寄らせないようにすることを目的にしていたようですが、それでも『家族の会』の誰もがあの人を犯罪行為をすることにさえ全く躊躇が無くなる程に憎悪していたことは間違いありませんでした。こんなことをして警察に捕まったらどうするのかなんてことは考えもしませんでした。私たちは多分、集団ヒステリーのような状況に陥っていたんだと思います。私たちはそれからすぐにあの人を縄で縛って、施設の中に閉じ込めました。子供の好きだったものを共有するために使っていた部屋に、施設の中で唯一外からのみ施錠できる鍵が付いていたので、おもちゃや服などは別の場所に移してその部屋をあの人を監禁するための部屋にしました。私たちはあの人を、思いつく限りの全ての方法で虐待しました。熱湯を顔に掛けたり、針を鼻や耳の穴に入れたり、カッターで全身を切ったりして、生かして苦しめ続けました。
それから数週間後、施設にまた別の知らない人が来ました。玄関のドアをノックして、『浜名宗吉くんを名乗る不審な人物を見かけませんでしたか』と呼び掛けていたようで、私は手話が分かる人と一緒に玄関先に応対しに行きました。その人は背の高いお爺さんでした。私はここで初めてあのストーカーを監禁していることが誰かに知られたらまずいと思って、とっさに『あの人は追い払った』と嘘をつきました。するとお爺さんは、『でしたら本物の子供を取り返すために親御さんにできることをお教えします』というようなことを言ってきたんです。その内容は、『自宅にある誘拐された子供の痕跡となるものを全てどこかに奉納して鍵を掛けておきなさい』というものでした。今冷静に考えてみれば全く理解できませんが、当時の私はまるで催眠でもされたように、これをすれば宗吉を取り戻せるんだと心から納得し、喜びました。他の『家族の会』の人たちもいつの間にか集まってきていて、同じように涙を流して喜んでいました。お爺さんは私たちに、『今日からは自宅以外の場所で寝泊まりしなさい』とも言ってきました。あのお爺さんは、おかしくなってしまった私たちが一斉に見た幻覚だったのでしょうか? あの時の記憶は夢の中のようにぼんやりしています。とにかく確かなことは、『家族の会』はその日から全く様変わりしたということです。
私たちはその後すぐ、別館の建設について議論を始めました。これからずっと寝泊まりしていくなら、ちゃんとした寝室や台所、洗濯場など生活に必要な設備を整える必要があったからです。当初は本館の横にもう一軒建てるつもりで別館と呼んでいたのですが、敷地の広さの問題があり、かつあのストーカーを隠しておくには地下が最適なのではないかという提案もあったので、話し合いの末に別館は本館の地下に建設することになりました。『家族の会』には家族経営の建築会社を取りまとめている高齢の夫婦がいらっしゃったので、その方々のご厚意のもとで、別館の建設は急ピッチで秘密裏に進みました。地下への階段は絶対に見つからないような隠し階段にしてもらい、施工に関わる全ての記録は後に抹消しました。別館ができるまでの間は、応接室に布団を敷いて雑魚寝しました。また、『お納め』は、ストーカーを監禁している部屋で同時に行いました。『子供の痕跡となるもの』は納めた後施錠して管理しなければならず、鍵が付いている部屋はやはりそこだけだったからです。『子供の痕跡となるもの』と言われただけなのに、私たちには何故か『その中には被害児童のきょうだいも含まれる』という共通認識があったから、『きょうだいのお納め』もその日からすぐに始まりました」
浜名氏の話を全面的に信頼するにはまだ早いだろうが、彼女の話は驚くべきものだった。我々は外部から見た状況証拠から浜名氏こそ人々を洗脳しおかしくした黒幕だと考えていたが、彼女もまた得体の知れない狂気に呑まれた一人に過ぎなかったのか?
「別館が完成して、ストーカーを元の部屋からそこに移動させようとした時の話は、先月号の記事にあった通りです。ストーカーはあの部屋から連れ出されるとき、そこに置かれていたトイレ用のバケツを振り回し、中身をぶちまけて抵抗してきたんです。ストーカーは自分が何をされても私たちに危害を加えるようなことはほとんどしてこなかったから、あの時は驚きました。『お納め』されていた被害児童のきょうだいの一人だった、先月号で取材を受けていた彼女は、その隙に施設を飛び出して行ってしまったんです。その後彼女の通報によって警察の強制捜査が施設に入った時は、ストーカーは別館で隠し通し、『きょうだいのお納め』も間一髪のところで誤魔化すことができたのですが、その反省からあの部屋はより厳重に管理されるようになりました。一人の誘拐児童に対して一つの個室を用意し、さらにそこにも鍵を掛けておくことにしたんです。そして、確かこの頃から、あの部屋は『跡奉』のための部屋と呼ばれるようになりました。『跡奉』については、そちらの記事では儀式の名前として扱われているようでしたが、あの儀式自体は『家族の会』では単に『お納め』としか呼ばれていませんでした。しかし、あの部屋が『跡奉』のためのものであるということは、一体誰が言い出したのかも分かりませんが、皆それを自然に受け入れていました。上手く説明できないのですが、『跡奉』という文字を見た時、私が意識するのは『お納め』それ自体ではなく、それよりもむしろ、何か『お納め』の目的のような、相手のような感じがあるんです。こんな感覚の話をしてもしょうがないでしょうか。
あのストーカーは、別館の端にある部屋に閉じ込めました。部屋といってもほとんどただの真っ暗な縦穴で、本館の裏手にあるハッチを開けると地上から直接ストーカーを覗けるような構造になっていました。この地上のハッチから食事の度に出る生ごみや残飯を混ぜたものを落として、ストーカーが飢え死にしないようにしていました。元々『家族の会』の他の人達がストーカーを痛めつけるのは二度とこの施設に近寄らせないようにするためでしたから、最初は様々な責め苦を与えながら『二度とここに近づかないと誓うまで拷問する』などと言っていました。しかしストーカーは一向にそれに同意しようとしなかったので、この頃になると皆も私と同じようにストーカーを拷問し苦しめ続けることそれ自体が目的になっていたと思います。『家族の会』のことを知って施設を訪問しに来た方は、『お納め』を見学して怒ったり怯えたりしていてもなお、ハッチからストーカーを一目見せて、『こうでもしないとこのような偽者が来てしまう』と伝えると、必ずあの儀式を受け入れてくれました。特に誘拐児童の母親は、ストーカーを見るなり私たちに非常によく賛同してくれました。私たちは増えていく会員と共に、別館を拠点にして共同生活を送りました。別館で起きて、朝の支度をして、職場に行き、そして別館に帰ってくる日々の中で、私たちは元々住んでいた家を忘れ、あの施設を新しい家だと思うようになりました。ストーカーへの拷問はずっと続き、この頃にはあの人はほとんど泣きも叫びもしない無気力な状態になっていました。
こうして『家族の会』の規模はどんどん大きくなっていきましたが、そうなるとその分、近隣住民や『お納め』された被害児童のきょうだいの通っていた学校、それにストーカーを見ないで帰ってしまった人たちから児童虐待の疑いがあるとして通報されることが増え、警察も本格的に『家族の会』を取り調べてくるようになりました。当時の私たちは、このようなことは『お納め』を中断させ私たちの子供を取り返したいという願いを踏みにじる外道じみた所業であると本気で信じていました。今となっては考えられないことです。子供たちを狭い部屋に閉じ込めて猿轡を噛ませることが、誘拐された子供を取り戻すことにつながるわけがありません。しかし私たちは皆、一切の疑問を抱かずこの儀式を受け入れていたんです。代表という立場にありながら、私は『家族の会』が壊れてしまったのが何故なのかという問いにはっきり答えることができません。あのストーカーは何だったのか、何故私たちはあのストーカーがあれほどまでに憎かったのか。あのお爺さんは何だったのか、何故私たちはあのお爺さんの言葉をそのまま受け入れ従ったのか。『跡奉』とは何だったのか、何故私たちはあの6年間、一度も正気に戻らなかったのか。ただ感情に身を任せて『家族の会』にいたあの時を振り返ると、何もかもがぼんやりしていて、本当は全て悪い夢だったんじゃないかとさえ思えてしまいます。しかし、それでも、あれは現実なんです。私は『家族の会』の代表として、何年間も大勢の子供を閉じ込め虐待したこと、ストーキング行為をしてきたあの人を拷問し、最後には地下に置き去りにしてきたことに、責任があります」
浜名氏の文章は、まるで自分で自分に言い聞かせるようなものになっていた。小さく息をつくと、彼女は9年前、『家族の会』が解散するに至った経緯を語り出した。
「解散の一年前くらいから、私たちも流石にぼろが出始めて、警察の強制捜査は次第に激しくなっていきました。拷問器具や未処理の排泄物が見つかったことで、警察は私たちが通報通りのことをしているという確信を強めていったんです。しかし、特別な操作が無いと現れない別館への隠し階段や、非常時は土で覆って隠すようにしていた本館裏のハッチは、入念な警察の捜査でも暴くことができませんでした。捜査が入る度に『お納め』していた被害児童のきょうだいは別館に移動させていて、ストーカーはもちろんその最奥に監禁していましたから、私たちの犯罪行為の決定的な証拠が掴まれることは無かったんです。別館は、ついに警察に見つかりませんでした。『家族の会』が解散することになったきっかけは、それからしばらくして、私が捜査に来た刑事を暴行して逮捕されたことなんです。あの事件の日、業を煮やした警察は私たちの情に訴えかけるような方法に打って出ていました。『家族の会』の会員を調べて、それぞれその人の子供の誘拐事件を担当していた顔見知りの刑事を集めて派遣し、私たちを説得しようとしてきたんです。宗吉の事件で最初お世話になっていた刑事の方も、もちろん来ていました。その頃にはあの人とはもう何年も会っていませんでしたが、あの人はいつの間にか習得してくれていた手話で、『我々は誘拐児童の捜索に全力を尽くし続けています』『我々が必ず宗吉くんを浜名さんの元に帰します』と、真剣に伝えてきました。そして、『だからこんなことは止めてください』『こんなことをしても宗吉くんは帰ってこないどころか、悲しむだけですよ』と、言ってきたんです。
私はその瞬間激昂して、持っていたカッターナイフであの人に襲い掛かりました。ストーカーに対する拷問の時と同じように、馬乗りになって何度も切りつけました。異変を察知した他の刑事たちは、すぐさま駆け寄ってきて私を取り押さえました。私はあの時、『お前に宗吉の何が分かるんだ』と、はらわたが煮えくり返るようでした。あのストーカーと同じように、この刑事は宗吉になりきって私を馬鹿にしているんだとしか思えませんでした。留置所に入れられた私はストーカーのことが露見するのを恐れて黙秘を貫き、そのまま傷害罪で懲役5年の判決を言い渡されました。そして、刑務所に入れられてすぐあった『家族の会』の人との面会で、私は『家族の会』が解散することになったと知らされたんです。面会にはもちろん手話を理解できる職員が同席していましたから、その具体的な理由をはっきり聞き出すことはできませんでしたが、私の事件をきっかけに施設への捜査がさらに進んで別館に気づかれる危険性が高まったからでしょう。元々ガスや水道の検針で地下に生活空間があることを推測されることは懸念していたのですが、それが現実のものになろうとしていたんだと思います。『家族の会』の会員は皆被害児童のきょうだいも連れて一旦自宅に帰ることにしたようで、儀式を再開する方法はそれから考えるのだと言いました。それから、『お納め』していた子供の物はまとめて別館に移しておいたということでした。不在の内に子供の物を警察に『空き巣』されたくなかったのでしょう。ストーカーはもちろん、『そのままにした』と仄めかされました。こうして、この面会を最後に、私と『家族の会』との関わりは途絶えました。
その後すぐに、私は再び捜査官に呼ばれ聴取を受けました。児童虐待やストーカーの拷問の証拠がついに見つかったのかと思いましたが、伝えられた話は到底信じられないものでした。『家族の会』の会員が皆行方不明になっており、さらに次々に殺された状態で発見されているというんです。被害者家族たちは、抵抗の形跡も犯人の痕跡もない中、ばらばらに北関東のいくつかの山に散らばって埋められ窒息死していたそうです。ストーカーの復讐という可能性も考えましたが、万が一別館を脱出していたところであんな痩せ細った体では人一人も殺害できないでしょう。ましてやこの不可解な事件を作り出せるはずがありません。警察は最初私が『家族の会』の皆を洗脳して自死を強要したという線で考えていたようでしたが、鑑識の結果明らかに人の手の加わった他殺であることが分かると、ずっと刑務所にいてアリバイのある私は犯人の候補から外されたようでした。結局この事件は完全に迷宮入りしてしまい、『家族の会』は一時解散という状態のまま完全に消滅しました」
この事件には聞き覚えがある。我々がこの「家族の会」を追うきっかけになった最初の取材で、白坂氏が息子夫婦の身に起きたこととして語っていたことだ。それに、これは北口氏の妻が失踪してしまったこととも符合する。彼女は家を出て「家族の会」の施設で暮らすようになり、そしてそのままこの事件に巻き込まれたことで姿を消したのではないだろうか?
「刑務所で服役するうちに、私は『家族の会』にいたときの激しい感情を忘れていきました。宗吉に会いたいという思いはもちろん変わりませんが、何度も語っている通り、自分がなぜあんなことをしたのか理解できなくなりました。5年が経って釈放される頃には、全ての記憶が荒唐無稽に思えて信じられませんでした。こうして私は、あの時の裁かれなかった罪を隠したまま社会に復帰し、新しい生活を始めました。私の話せることは、これで全てです」
我々調査隊は、この一連の悲劇は全て浜名氏が裏で糸を引いていたものとばかり考えていた。しかし、あの「家族の会」の恐ろしい行いの数々を生み出したのは、代表である浜名氏ではなく、むしろ集団的な狂気だったのか? では、その狂気を生み出したものは何だったのか? 全ての始まりとなったあの「ストーカー」に関して、我々には一つ疑念がある。彼は本当に「偽者」だったのだろうか。先月号の稲田氏の証言、そして今回の浜名氏の証言の中に現れる「ストーカー」の行動は、宗吉くんを名乗り嫌がらせを行う人物というよりもむしろ、宗吉くん本人と考えた方が明らかに筋が通ったものとなる。我々がこの考えを浜名氏にぶつけると、彼女は目を丸くして紅潮し、震える指がキーボードを引っ掻くように蠢いた。緊張をはらむ数秒の硬直の後、彼女はそれを真っ向から否定した。
「ありえません。親が帰ってきた子供を偽者と勘違いするということが、本当にあると思いますか? 私を疑っているのは分かります。確かに私の過去の行いはどれも正気のものではありません。しかし、自分の子供を偽者だと思い込むなんて馬鹿らしい話は絶対にありえません。宗吉は私の一番大事な、私の命よりも大事な息子なんです。私が、その宗吉を、間違えて偽者だと思って、追い出して、監禁して、6年間いたぶり続けたと言うんですか?」
浜名氏は大きく息を吐いて続けた。
「すみません。感情的になってしまいました。今の私には、そう言って怒る資格もありません。私はこれから警察に出頭して、全てのことを洗いざらい自白します。『お納め』のことも、別館のことも、そこに放置したストーカーのことも、私が『家族の会』の代表として犯した全ての罪を伝えます。あなたたちには感謝しています。あなたたちの記事が無ければ、私は自分がやったこと全てを有耶無耶にしたまま生きていったでしょう。そんなことでは、宗吉の帰りを願う資格がありません。きちんと罪を償って、正しい人間になってからでないと、私には宗吉の帰りを願う資格が無いんです」
浜名氏の証言を元に警察の捜査が再開すれば、多くのことが明らかになっていくだろう。「ストーカー」の死体がまだあの地下空間に閉じ込められているままなら、彼の正体はDNA判定で暴かれることになる。「別館」から見つかる新しい証拠が、あの迷宮入りした「家族の会」解散直後の不可解な殺人事件を解明する助けになるかもしれない。この調査は警察に一任しよう。それでは、我々が取り組むべきことは何か――あの老人の調査だ。我々調査隊の取材活動を追跡し、宗吉くんを捜しているあの背高の老人男性の正体は、未だ闇の中である。しかしその特徴は、浜名氏の記憶にある、施設を訪れ「お納め」の儀式を指示したあの「お爺さん」に通じるものが無いだろうか? 今回の取材に際してこの老人は現れなかったが、彼が我々の動きを監視していることに疑いはない。今まで我々は身の危険を感じあの老人との接触を避けてきたが、最早この調査は彼を追わずして終えることができない段階に突入している。我々はこの先、あの老人を追跡し返すことに尽力する。長くなったが、この老人に関して何か情報を持っている者はぜひとも月刊テンポ・ルバート編集部オカルト係に問い合わせてほしい。それでは読者諸君、次号の「となりのオカルト調査隊」でまた会おう。
青梅市カルト児童集団監禁事件捜査資料:北関東広域に分布する不審な捜索願
浜名宗吉君を捜しています。目を離した隙に居なくなってしまいました。何処を捜しても見つからないのできっと元の家のそれも親御さんにも見つからないような場所に黙って隠れているのだと思います。ですから親御さんに言い聞かせて宗吉君が住んでいた家は無くしました。家の中身は絶対に盗まれたり戻されたりしないよう施錠させ一部は結局自分で埋めました。これで隠れる場所は絶対に無い筈だが何故か見つかりません。涙を流し途方に暮れています。浜名宗吉君の居場所を御存じの方は御迎えに上がりますので教えてください。扉の前で呼びますから家から出てきてください。
「拷問し地下に置き去りにした」と代表の女が自首 9年前の未解決カルト事件に関連か 東京都青梅市(2014年9月16日)
「関東地方誘拐被害児童家族の会」が所有していた東京都青梅市の施設の地下から少年のものと見られる白骨化した遺体が見つかった事件で、警視庁は16日、同会の代表を務めていた浜名亜実容疑者(42)を傷害の容疑で逮捕した。警視庁によると、浜名容疑者は14日、近所の交番に出頭して「施設の地下で男を監禁・拷問し置き去りにした」と供述し、捜査の結果白骨化した遺体が見つかった。浜名容疑者は他にも、施設で誘拐被害児童を取り戻すための儀式と称して児童を監禁したことを供述しており、警視庁は「青梅市カルト児童集団監禁事件」捜査本部を新設して詳しい状況を調べている。
「関東地方誘拐被害児童家族の会」の施設は、1999年から2005年にかけて児童虐待の疑いで計5回に渡る強制捜査を受けていたが、いずれも証拠不十分とされ立件には至っていなかった。2005年の強制捜査の際、浜名容疑者は捜査員に刃物でけがをさせたとして傷害罪で懲役5年の判決を受けている。同会は2005年に解散したが、収監されていた浜名容疑者を除く会員とその子供全員が直後に殺害されたまたは行方不明になった事件があり、この事件は不可解な点が多く未解決のままである。
浜名容疑者は、動機について「自分の誘拐された息子を騙ってつきまとい、嫌がらせをしてきたから」と述べている。以前の強制捜査では施設に地下空間があることは発見されていなかったが、浜名容疑者の証言に基づく捜査の結果地下への隠し階段が発見され、施設の全貌が明らかになった。警視庁は、少年とみられる白骨化した遺体の身元も含めて、未解決の元会員連続殺人事件との関連も視野に入れて、この「青梅市カルト児童集団監禁事件」に関する徹底的な捜査を行う方針だ。
関東地方民俗大辞典第三版(抜粋)
【シヤカマイヌ】
埼玉県全域と群馬県南部にかけて使われていた食犬または食用の犬の隠語。地域の有力者の間に遊びで犬を嬲り殺して食うことが流行すると、食用の犬を育て密かに犬肉を提供する商人が現れ繁盛したことが淵源らしい。店頭に「シヤカマイヌ」と出しておくことで食犬の提供を示したと言うが、言葉の意味は判然としない。漢字では「士屋釜犬」の他に「蛇窯犬」といった表記が確認されており、「蛇窯」は朝鮮伝来のものであって朝鮮には犬食文化があることなどから、最初はその関係で隠語として朝鮮の蛇窯を取って来たが「じゃがま」と読み損なって普及したのでないかとの説がある。今日では殆ど表立っては使われていないが、悪態としてこれを髣髴する「ヤカマ乞食」という文句が同地域に流布している。
【釈迦濯ぎ】しゃか-ゆすぎ
茨城県北部で見られる年中行事。地域により異なるが多くは二月の第一週に一日で行われ、村中の仏像を寺に持参して水でもって清める。これにより人の心が清められ悪事が減ると信じられている。この行事にまつわる逸話はいくつかの種類が流布しており、最も有名なのは綺麗好きで信心深い青年が毎日木の仏像を水で洗滌していたが、あまりにも頻繁に洗うので仏像には黴が生えて首が腐り落ちてしまい、その夜青年は仏像と同じように頭が腐って死んでしまったので、以来仏像を水で洗う日は年に一回に決めたというものである。青年が夜なべして首の無くなった仏像から小さい五体満足の仏像を彫り出したので難を逃れることができたという変種もある。言い伝えとは違いこの行事の日でなくても各家庭では定期的に仏像を洗うようだ。
【シャクブ】
主として北関東に伝わる怪異。姿は六尺程の背の老翁とされ、家の外にいる子供の居場所を感知し一人の時に攫ってしまうという。攫われた子供はなぶりものにされ言語を絶する苦痛を与えられる。多くの脱出譚が知られているが、凡て家族の元に帰っても呪いのせいで偽者と思われて爪弾きにされ、家の中に入れず再び攫われるという結末を迎える。偽者にされた子供は、大人なら誰が見ても甚だしくこれを嫌忌拒絶し一刻も早く追い払いたくなるらしい。子供なら蛆が湧いたり骨だけになった死体であっても攫う。家の中には入れないとされるが、どうやら狙っている子供の過ごした痕跡のある場所として家を理解しているようである。漢字では「借夫」という表記の他に「迹奉」や「跡奉」といったものがあり何れも由来は分からない。
灰
小さい頃、母さんはいつも私に、人通りの少ない道を一人で通ってはいけないと言って聞かせた。もしそんなことをしたら、私は跡奉に攫われて、母さんも父さんも私のことが分からなくなってしまうんだよ、とおどかされた。私は怖くなって泣いてしまった。もちろんほんの数年後には、あれは子供を本当の誘拐から守るための、よくあるしつけ用の迷信だったんだと分かった。夜に爪を切ると親の死に目に会えない、とかいうのと同じように。けれど、あの話の「私のことが分からなくなってしまう」っていう部分は何だかすごく不気味で、ずっと印象に残っていた。何か得体の知れないものに攫われるっていうだけで、子供にとっては十分怖いでしょう。じゃあ、あんな設定まで付け足さなくてもいいじゃない。
大人になってからふと思い立って調べてみると、跡奉はあまり世間で知られていない割には古い民話がそこそこ残っているみたいで、試しに読んでみたら結構怖かった覚えがある。特に、玄関で親に追い出されたけど、機転を利かせて屋根裏に隠れた子供の話。跡奉はその子供を感知することができなくなり、必然的に家の中に隠れているということに気づく。でも家の中に入ることはできないから、玄関で親を呼び出して、その親に家の中で子供を捜させる。もちろん、「偽者が家に潜んでいるから捜し出して追い払いなさい」みたいなことを言って。それでも子供は賢くて、あの手この手で親に見つからないように隠れる。すると業を煮やした跡奉は、今度は親に、「居なくなった子供の痕跡を全て家から出しなさい」と言う。親は子供のおもちゃや服はもちろん、その子供と一緒に過ごしたきょうだいも家の外に出す。その子供がいたことを覚えている、痕跡の一つだから。そして、最後に両親も家の外に出て待機する。その瞬間、跡奉は何でもないように玄関をくぐれるようになって、真っ直ぐ子供が隠れている場所に行く。あの子供の家は無くなってしまいました、と言って、話は終わる。
最初の手紙が来た時はただの偶然だと思った。旦那の言う通りあれは儀式の名前であって、母さんが教えてくれた「跡奉」とは関係ない話だろうと思った。だけど、香織が使っていたものを、息子夫婦が指定した宛先の通りあの会の施設に送った時、頭の片隅にあの話があった。私は自分に呆れかえった。香織が攫われてしまったのは私のせいなのに、どうしてこんな意味の分からないことを考えていられるんだろう、と思って泣きたくなった。あの手紙に、私がこっそり何枚も息子夫婦宛てに書いて送っていた謝罪の手紙に対する反応が一言もなかったのが、一番つらかった。いいえ、愛娘が攫われてしまった息子夫婦の方がよっぽど辛いに決まっているのに。
二枚目の手紙が届いたとき、私は胸が張り裂けそうだった。あの会はカルト団体だった。息子夫婦は、きっと同じような境遇で苦しんでいる仲間と話がしたかっただけだったのに、洗脳されおかしくなってしまっていた。全て私のせいで。私があのとき、ちゃんと香織を見ていれば、こんなことにはならなかった。私たちはずっと幸せに暮らしていけた。私は声を上げて、震えて泣いた。だけど、少し落ち着いて、あの手紙をもう一度頭から熟読していると、私はまた跡奉の話を思い出してしまっていた。おもちゃに、服に、きょうだい。考え始めると止まらなくなった。どうにかして無意識に気を紛らわせようとしていたのかもしれない。最初に思ったのは、あの異常に憎まれている「ストーカー」は、跡奉に誘拐されて逃げてきた子供なんじゃないかということだった。それは、もしかしたら、香織かもしれないということでもある。そんなこと考えたくもないけれど。
跡奉の呪いで、攫われた子供は全ての大人から偽者と思われるようになる。大人はみんなその偽者にひどい嫌悪感を抱き、追い出そうとする。そういう話を聞いた時、私は少し疑問に思った。ひどい疑問でしょうけど。皆が皆、ただ追い出すだけで満足するのかしら、って思った。大人の中には偽者を殺そうと思う人もいるんじゃないか。あるいはもっとひどいこと、例えばずっとどこかに閉じ込めて、生かして痛めつけ続けるとか、そういうこともありえるんじゃないかって思った。世の中には子離れできない親みたいな人もいるけれど、そういう子供に格別の執着を抱いているような人が、子供を誘拐されておかしくなりそうになっている時、その子供の偽者に出くわしてしまったら。呪いによる異常な嫌悪感も相まって、ただ追い払うだけでは済まないような気がする。全く知らない人が、自分の最愛の子供の名前を名乗って、自分にずっとつきまとってくるんですもの。陸も陽菜さんも香織に対してそんな風ではなかったと思うけど、どうだろう。とにかく、呪いのせいで気持ちの悪い偽者としか思えない自分の子供を、「ストーカー」と呼んで監禁し、虐待するのは、いかにもありそうな話だと思った。いかにもありそうで、なんて気分の悪い話。
ここからは完全に妄想の域だけど、あの会は元々、跡奉とは一切関係なしに、誘拐された子供のおもちゃなんかを持ち寄って共有していたのかもしれない。その中に、あの「ストーカー」と呼ばれていた子供のものもあったのかもしれない。だとすると全ての話の筋が通る。子供の痕跡が置かれている施設に、偶然にもその子供を閉じ込めてしまったら、跡奉はその子供を感知することができなくなる。跡奉が従うルールでは、その建物が子供の「家」になってしまうから。そうなると、跡奉はあの話と同じように子供が家の中に居るということには気づくけど、会の施設が新しく「家」になっているとは思わず、元々住んでいた家に隠れていると勘違いする。そして、親に言ってその家にある子供の痕跡を全て外に出させようとする。おもちゃも、服も、きょうだいも、何もかも。跡奉の指示が狙いの「ストーカー」の親だけではなくあの会にいる全ての親を従わせることになる確証はないけれど、少なくとも言えるのは、跡奉にとって子供が家を失うことはいつでもプラスになるということ。あるいはもしかしたら、この「儀式」は途中から跡奉の意図すら離れて、単にあの会の中で自己目的化して拡大していたのかもしれない。子供を取り返したいと必死で願う精神的に不安定な親たちに、「ストーカー」という共通の敵に対する異常な憎悪が結びついたことで、あの会は「儀式」と拷問を行うカルトに変貌して、信者を増やし団結し続けたのかもしれない。
馬鹿らしい願望かもしれないけれど、そうすると、息子夫婦はこの頃あの施設で生活していたのかもしれないと思った。きょうだいと同じ理由で親も家から出ないといけないのだから、当然あの会の親たちはおあつらえ向けの会の施設で寝泊まりするはずだ。それだから、二人は私の出した手紙に反応しなかったのかもしれない。私の謝罪を無視しているのではなくて、単に息子夫婦は長い間家のポストを見ていなかっただけなのかもしれない。そう思うと少し楽になって、でも次の瞬間には自分が嫌になった。手紙には、あの会が一旦解散すると書いてあった。そうしたら、親たちはどこに行くことになるのだろう。自分の家に帰るのかしら。でもそうなると。
とりとめなく想像を続けていた時、旦那が帰ってきて、私は思わずとっさにあの手紙を隠してしまった。息子夫婦がこんな風になってしまったことを知られたくなかった。「お前が香織をちゃんと見ていなかったせいでこんなことになってしまった」と言われるのが怖かった。旦那は間違ってもそんなことを言う人じゃないって分かっているのに。我に返って、もうあんな変なことを考えるのは止めようと思った。私は現実と空想の区別がつかなくなっているのかもしれないと思った。子供のしつけのための幽霊話にすがって、現実から目を背けていた。香織が居なくなってしまった現実から。二人がカルトに狂わされてしまった現実から。だけどあの電話で、息子夫婦が不可解に殺されたと聞いた時、私は結局、ああ、跡奉が殺したんだ、と思った。跡奉は、皆の家が無くなったままの方が良かっただろうから。子供の痕跡の一つである親もきょうだいも、家に戻したくなかっただろうから。
全部書いてすっきりした。私は香織が居なくなってから、罪悪感に押しつぶされて、頭がおかしくなったんだと思う。最近はこんな妄想を一日中している。年のせいもあるのかしら。このノートと息子夫婦からの二枚目の手紙は、一緒に庭で焼いてしまおう。ノートは誰に見せるようなものでもないし、こんな内容が誰かに見られたら困ってしまう。あの手紙は、旦那が見たら悲しむだろうし、何よりあの人のことだから、あの会で一体何が起こったのかを詮索し始めるでしょう。あの人は不器用だから、愚直にご近所さんに聞いて回って、「あの家の息子夫婦はカルト信者になって死んだ」みたいな噂を立てられてしまうかもしれない。それはちょっと、あなどりすぎかしら。そうでなくても、あんなものを残しておいたら一体いつひょんなことから息子夫婦の悪い噂が広まるかも分からない。そんなことになったら私は、本当に私を許すことができない。今でもだいぶ、そうなんだけれど。
それに、まだ跡奉は「ストーカー」を攫いなおせていないかもしれない。あの会が解散し、息子夫婦が殺されてからもう五年が経つけど、あの会のニュースはまだ流れてこない。「ストーカー」は、警察の何回もの強制捜査でも見つからなかった施設の秘密の場所に閉じ込められたまま、今も見つかっていないんだと思う。実はとっくに跡奉に持って行かれていて、そもそも見つかる遺体が無いのかもしれないけれど。でも、「ストーカー」にされてしまったあのかわいそうな子の物があの施設に残されている限り、跡奉はあの子を攫えない。もし今でも、あの施設があの子の「家」であり続けているなら、あの会のことを詮索するのはもうやめたほうがいいんじゃないかと思う。
止まっていた時間が動き、新しい手掛かりが見つかって、施設が再び根こそぎ捜査されたら、ついにあの子の遺体が施設の外に出されるかもしれない。あるいはその子のおもちゃや服が証拠品として押収されて、とにかくあの子と「痕跡」、そして施設は離れ離れにされてしまう。そうしたら、あの子は最後に残った「家」を失ってしまう。跡奉は喜んで、ついにその子を攫うでしょう。真実を知るのも大切かもしれないけれど、誘拐され、必死の思いで帰ってきたのに、親に偽者と呼ばれ、監禁され、拷問され、放置され、最後は飢えて死んだあの不幸な子のことを、もうそっとしておいてあげた方が良いと思う。あの子の正体が香織であるにしても、別の知らない子供であるにしても。跡奉の手元に戻って再びひどい拷問を永遠に受けることになるよりは、暗く狭い、苦痛と絶望の記憶に満ちたあの「家」の冷たい床の上であれ、朽ちて静かに眠る方が遥かにましでしょう。だから、私は誰にもあの会のことを詮索してほしくない。あの会の狂気を紐解くヒントを、誰にも見せたくない。そのきっかけを、万が一にも、誰にも与えたくない。そのために私は、あの会の悪事の証言を握り潰す。あの二枚目の手紙は、絶対に読まれないよう、確実に焼き捨てる。このノートと一緒に。
まったく、私は何を言っているのかしら。そんな可哀想な子は、きっと私の妄想の中にしかいないのに。さようなら、ノートさん。びっしり書かれた中身は全部、狂った老人の世迷言。あなたには手紙と一緒に灰になってもらいます。誰にも私の狂気が気づかれないように。誰にも二人の噂話ができないように。誰にもあの子が、これ以上辱められないように。
月刊テンポ・ルバート2014年11月号掲載「休載のお知らせ」
浜名宗吉君をようやく見つけることが出来ました。嬉しいです。皆様一丸となって詮索して頂き助かりました。御協力大変有難うございました。
|